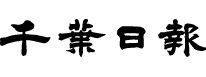真っ暗な部屋、泣き止まない我が子を抱きながら「この時間が永遠に続くのではないか」と不安になる子どもの夜泣き。千葉県内では今年9月、長男(3)を布団に巻いて死亡させたとして、母親(27)が逮捕された。母親は警察に対し「夜泣きが耳をふさぎたくなるほどだった。近所のことも気にした」と供述したという。子どもの夜泣きで不安になり精神的に追い詰められる保護者たち。こうした中、子育て中の親が夜中にチャットルームに集まって励まし合ったり、夜に開所する子育て支援センターを訪れたりするなど、令和の今、オンラインとリアルで支援の場が広がりつつある。専門家は「1人で抱えず誰かに相談して」と呼び掛ける。(デジタル編集部 町香菜美)
オンラインで交流、励まし合う
「夜勤(夜泣き対応)、1時間おき」「こちらも1時間おき。つらいですね」「寝かせてくれー」…。夜も更けたころ、LINEのオープンチャット機能を使った「オンライン夜泣き小屋」には母親たちの叫びが次々に投稿される。切実なつぶやきに対し、同じ時間帯に起きている母親からリアルタイムに反応があることも。この「夜泣き小屋」は、漫画家のかねもとさん=東北在住=が2019年8月に開設した。
かねもとさんは2児の母で、2人とも夜泣きをする子だった。特に第1子は、ベッドに寝かせた瞬間に泣き出し、一晩中抱っこして過ごすような日も少なくなかった。ある時、夜泣き対応中の母親たちが集まり励まし合う想像の「夜泣き小屋」をエッセー漫画にしてSNSに投稿。大きな反響があったことなどを受けて、「オンライン夜泣き小屋」を立ち上げた。

現在、「夜泣き小屋」は800人前後が参加し、管理は別の人が引き継いだ。かねもとさんは「ここがあって良かったと言ってもらえることが多かった。距離や時間などを気にせず、特定の誰かに話しかけるわけでもない独り言を拾ってもらえる。実際に会って話すよりもドライではあるが、対面ではできない交流ができるのもオンラインの強み」と話す。
夜にともる明かり
一方で「リアル」な支援の場もある。松戸市の「ドリーム子育て支援センター」は午後10時まで開所。夜間に利用できる子育て支援センターは全国的にも珍しい。
スタッフと談笑していた育児休業中の会社員女性(34)=同市=は、夫の帰りが遅く長女(2)と次女(0歳4カ月)を1人で見る時間が多いという。息が詰まるような思いの中、センターに救いを求めるようになった。女性は「下の子は夜泣きもあって、何をしても泣くので『どうしたら良いか』と悩むこともあった。スタッフの方は『大変だよね』と受け入れてくれるので助かります」とほっとした表情を見せる。多い時で週1回ほど通っているという。

同センターは社会福祉法人「さわらび福祉会」(和田泰彦理事長)が運営し、0歳~未就学の子どもと保護者が利用できる。保育士や社会福祉士の資格を持つスタッフが保護者に寄り添いながら根気よく話を聞く。
1人で家事と育児をこなし、夫の帰りを待つ時間帯は「魔の刻」(同センター)とも言われ、疲労からイライラが募り気持ちが暗くなりがちだ。訪れる人の理由はさまざまで、夜泣きの相談のほか、子どもがなかなか寝つかない、夫が在宅勤務のため「静かにしないといけない」など。子どもに発達障害がある人が「静かな環境で子育ての相談をしたい」と訪ねて来たり、「ここに来なければ手をあげていたかも」と深刻な状況だったりする場合もあるという。
「魔の刻」に来所した保護者は子どもを遊ばせながらスタッフと話すことで、安心した表情を見せる。

新型コロナ禍では一時閉所したり予約制にしたりしたが、今は多い月で30人ほどが来所する。スタッフの1人は「人が来ない日もあるが、開けておくことに意味がある」とうなずく。和田理事長は「顔を見れば保護者とスタッフの距離も縮まり、『心地よいお節介』ができる場所。ここに来れば何とかなる。悩みはそれぞれだと思うが、一人で思い詰めず頼れるところを頼ってほしい」。日が暮れた夜も、こうこうとセンターの明かりをともし続けている。
抱え込まないことが大切
厚生労働省による産後の母親を対象にした調査(2018年)では、「十分な睡眠がとれない」ことに不安や負担を感じた母親が、産後2週未満で54・2%、産後2~8週で49・2%と約半数を占める。子どもの夜泣きにより、母親が睡眠不足で不安を抱えるケースは少なくない。

小児科医で睡眠の専門家の東京ベイ・浦安市川医療センターの管理者、神山潤さん(67)は泣いている赤ちゃんを寝かしつける方法として、理化学研究所(理研)などのチームが発表した実験を挙げ「抱っこして5分歩き、落ち着いたら座って8分間ほど待ってからベッドに寝かせるという方法もある」と説明する。
一方で、「『子どもが寝ないのは自分のせい』と親御さんが自分を責めてしまい、その親のいらいらは子どもにも伝わり悪循環になる」と指摘。赤ちゃんの眠りは千差万別で子育てに正解はないとも話し「悩んだら行政や病院、子育て支援センターなどいろいろな所に相談してほしい。1人で抱え込まず、子育ては良い加減に『いいかげん』に肩の力を抜くことが大切」とアドバイスした。
※この記事は千葉日報とYahoo!ニュースによる共同連携企画です