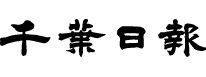2023年8月7日 05:00 | 有料記事

関東天然瓦斯開発のガス井戸。深さ約720~1400メートルの地層から天然ガスを含む地下水を採取している=茂原市に隣接する長生村

ガス井戸の掘削に使った上総掘りの道具を説明する千葉彌幸さん=茂原市上永吉

昌平町のガス利用組合が作った貯蔵施設跡。近くには当時の経緯を刻んだ石碑もある=茂原市茂原の稲荷神社
外房の中核都市・茂原の歴史を語る上で欠かせないのが、地中に眠る天然ガスの存在だ。明治時代には住民が利用組合を組織して産業発展の火をともし、有用性に着目してさまざまな企業が進出した。資源の輸入価格が高騰する中でも料金が変動しない「千産千消」のエネルギーとして、改めて注目されている。
千葉県の天然ガスは南関東ガス田と呼ばれる埋蔵地から産出され、地下水に溶けた状態で眠っている。外房地域では比較的浅い地層から採取でき、大多喜町や茂原市では明治時代から利用されてきた。
「燃ゆる気」とも呼ばれた天然ガスを茂原で採掘した先駆者の一人は ・・・
【残り 1486文字、写真 1 枚】